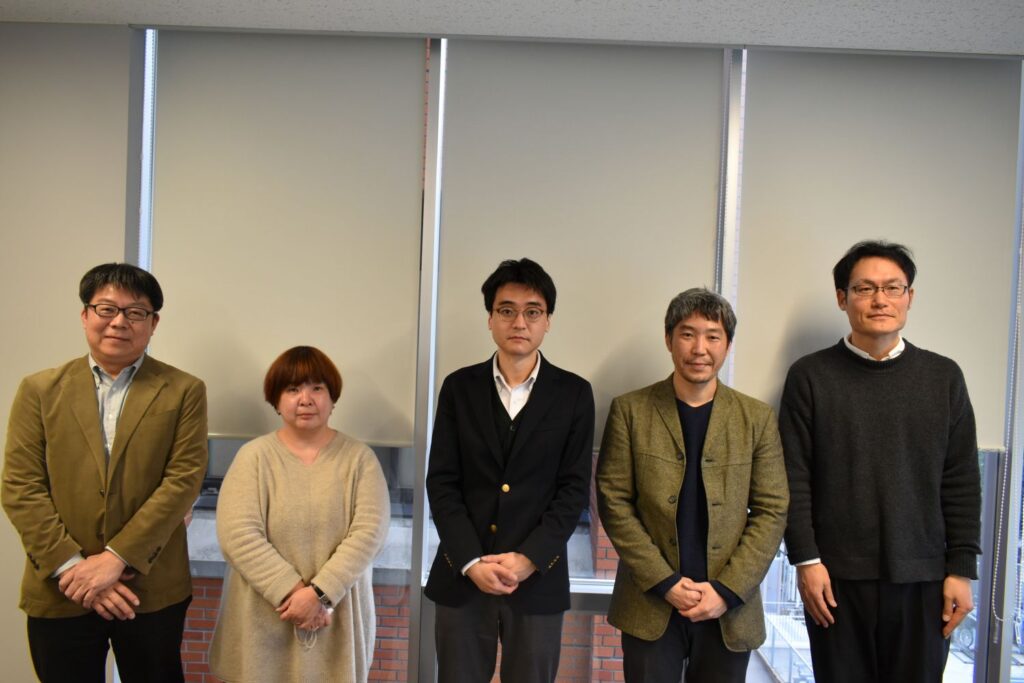【報告】少年教化班・公開研究会「仏教社会事業の一断面」【世界仏教文化研究センター 応用研究部門】
2026.02.13
2月7日(土)14時より、本学深草キャンパス燈炬館において公開研究会「仏教社会事業の一断面」が開催された。はじめに中根真氏(本学教授)による趣旨説明が行われ、その後、二件の研究報告がなされた。

最初に、広川義哲氏(本学准教授)による研究報告が行われた。広川氏は、近代本願寺において刊行されていた機関誌『教海一瀾』を収集・分析し、同誌に掲載された「社会事業」に関する記事の実態について報告した。『教海一瀾』には、婦人会や日曜学校をはじめとする社会事業に関する記事が多数掲載されており、当時の教化活動の様相を知る上で重要な史料である。
なかでも広川氏は、1927年に営まれた明如上人二十五回忌の記事に注目した。同法要に際して「映画伝道」が実施されていた点は注目に値する。当時、映画は青少年教育に悪影響を及ぼすと懸念される側面もあったが、そのような時代状況を踏まえると、本教化活動はきわめて先駆的であったといえる。一方で、この時期は「教育映画」の名目による映画上映が活発化し始めた黎明期でもあった。実際に、大阪では1933年度に422回もの映画会が開催されている。また『教海一瀾』には、関東大震災に関する記録映画の制作についても言及がみられ、当時の世相が反映されている。活動弁士と映画が教育や教化の手段として広く活用されていた状況がうかがえる一方、映画を用いたプロモーションが過剰化しつつあった側面も指摘された。高橋辰二のルポルタージュによれば、農村の青少年が動員され、日露戦争を賛美する文部省推薦映画を弁士の解説付きで鑑賞させられていた事例も確認される。
当時、活動写真は大衆にとってきわめて身近な娯楽であった。明治44年に実施された児童へのアンケートでは、77%が夏休みの娯楽として活動写真を観に行ったと回答している。丁稚や子守などを通じて一定の賃金を得ていた児童も多く、映画鑑賞という娯楽を享受する環境が存在していたことがわかる。ここで重要なのは、映画という媒体が、娯楽であると同時に教育・教化の手段としても受容されていた点である。さらに広川氏は、『教海一瀾』に掲載された広告にも注目した。とりわけ「クラブ練歯磨」などの商品広告が目立ち、当時、デパートガールやエレベーターガールといった女性像が広告の前面に押し出されていた社会状況が反映されていることが指摘された。また、仏具広告のほか、満州事変や愛国教育の影響を受けた広告も多く、誌面全体に世相が色濃く投影されている。
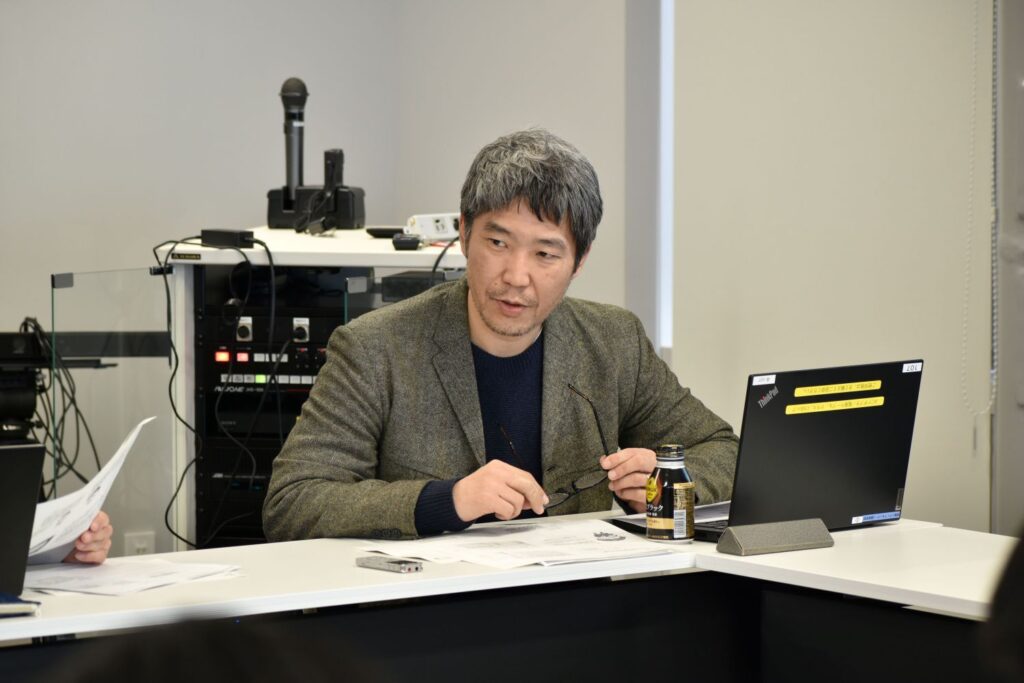
1938年には『教海一瀾』のリニューアルが打ち出され、教化雑誌としての性格がより強調されるようになる。それに伴い広告のレイアウトも変化し、従来は本文と境界が曖昧であった広告が明確に区別され、視覚的に広告と認識できる文体へと移行していった。この変化は、サイレント映画からトーキー映画への移行や戦時体制の進行とも連動しており、教化メディアとしての「訴求力」が高まっていった過程と捉えられる。
広川氏は以上の分析を踏まえ、『教海一瀾』を通して本願寺の教化事業をメディア論的に再把握する可能性を提示し、報告を締めくくった。
続いて、佐々木政文氏(京都先端科学大学准教授)より「新体制運動期における転向者と教誨師出身保護司」と題して研究報告が行われた。報告では、日中戦争期における真宗僧侶の役割について、革新派勢力との関係を軸に考察がなされた。特に、かつてマルクス主義者であった転向者が政府関連組織に参画し、大政翼賛会のもとで戦争に関与していく歴史的状況の中で、真宗僧侶がいかなる言説を彼らに向けて展開したのかが主要な関心点とされた。

佐々木氏は、上述転向者と真宗教誨師との間に間接的な関係があったことを指摘する。教誨師はいわゆる「真俗二諦説」に依拠し、結果として絶対主義やファシズムを追認する役割を果たした側面があるといわれることが多い。しかし先行研究では、エビデンスに基づく精緻な検討や、「国民総動員」という当時の制度との関係性の分析が十分ではないと佐々木氏は指摘する。1936年の「思想犯保護観察法」施行以降、教誨師は思想犯に対して「保護司」として教育・指導を行う立場となった。記録によれば、教誨師出身の保護司は、本願寺派で13名、大谷派で10名確認されている。転向者の中には、当初は浄土真宗の信仰を保持する者も少なくなかったが、1938年以降、その影響力は次第に後退していく。一度は真宗信仰の立場からマルクス主義を否定した小林杜人も、革新派として新体制運動を肯定的に解釈するようになった事例として紹介された。
1940年の近衛文麿内閣成立後、新体制運動は急速に進展し、同年には大政翼賛会が発足する。東京保護観察所は、「独自の政治的指導性を持つべきではない」との立場を取っていたが、転向者と保護観察所長の間では見解の相違が生じた。同年8月15日に開催された新体制座談会での議論からは、両者間の緊張関係が読みとれる。秋以降には、新体制運動に対して「社会主義者・共産主義者による運動ではないか」との批判が高まり、大政翼賛会内部でも彼らを排除すべきとの言説が広がった。小林一三商相による公然たる批判もその一例である。転向者の参画により、大政翼賛会が「赤の運動」と見なされることへの懸念があったためである。本願寺派教誨師の寺西は転向者の活動を「明るい展望」として擁護したが、非教誨師系の保護司は政治的関与に批判的であり、議論は最終的な結論を見なかった。ただし、決議としては「職分・職域を通して協力する」ことが確認されたのである。
教誨師出身保護司は、転向者に対して軽率な言動を慎むよう注意していたものの、積極的にファシズムを推進したとする記録は確認されない。その行動には、仏教的素養よりも、保護観察所職員としての立場が強く反映されていた可能性が示唆された。その後、「企画院事件」を契機として転向者の再検挙が進み、彼らの新体制運動は権力側から「共産主義運動と同然」と評価されるに至る。結果として、保護司もまた、その批判の渦中に巻き込まれたと考えられる。
両報告の後、全体ディスカッションが行われた。議論では、活動弁士とはどのような人物が担っていたのかという点や、当時の保護観察所による厳格な監視体制、新体制運動に対する国家の強い介入などが話題となり、活発な意見交換がなされた。議論は尽きず、盛会のうちに研究会が締めくくられた。